
1か月半におよぶ「修羅場であり地獄」を乗り越えるために、トップはどのようにリーダーシップを発揮したのか――。
「どんなリハビリの現場でもクラスターは起こりうる。自分たちの能力や想定を超えた事態に遭遇した時、
できることを淡々粛々とこなしていくしかないことを知ってほしい」
そんな思いから院長の酒向正春さんがATTENTIONの取材に応じてくれた。
取材・文/中保 裕子 写真/吉住 佳都子
感染対策の専門家の
視点を入れる
ねりま健育会病院は、2017年に開設された「大泉学園複合施設」内にある回復期病棟100床であり、介護老人健康保健施設80床の他、訪問リハビリや居宅介護支援事業所などを併設している。(開設の経緯については、ATTENTION創刊号でもインタビューさせていただいた。) リハビリ医療資源に乏しい練馬区で、“脳リハビリ医”酒向さんの実践する“攻めのリハビリ”は地域からの期待が集まり、回復期・老健ともに開設以来、常にほぼ満床。そんな中で新型コロナ陽性のクラスターが起きたのは2020年11月末のことだ。
「最初の3人の患者さんと少し増えうる患者さんの感染が止まれば終息するだろうと思ったのですが、その見通しは甘かった。新型コロナは発症数日前から感染します。最初の数日でこれは大変なことになっているというこわさを持ちました。感染は終わらないかもしれない、と」
未知の感染症を前に、何を基本に行動すればよいか――酒向さんはまず外部の感染管理の専門家の目で自分たちの現場を見てもらうことが必要と考えた。ちょうど東京に出張中の高山義浩医師(沖縄県立中部病院感染症内科)と個人的な知己であったことから病院に来てもらい指導を受けることができた。高山医師の見立ては「終息までには2か月かかるだろう」というものだった。それは、当初の酒向さんの予想より厳しいものだった。専門家の指摘により、密接と密集を核にした良質なリハビリを提供していたことが却って感染リスクを高めることにつながってしまった、というショッキングな事実も明らかになった。
「私たちは“患者さんとご家族の心と気持ちに寄り添って支える医療、そして、その回復の喜びを共有する医療”をモットーにリハビリテーション医療を提供してきました。認知症や不穏の患者さんが多いとスタッフ1人が同時に3~4人のリハビリをサポートせざるを得ません。一人の患者さんを支えている間、動く別の患者さんが転倒しそうになる。それを止めるには、手で支えるしかなく、その間は一瞬です。支えるための手をアルコール消毒している時間はありません。高山先生は私たちの医療の質や理念をよく理解してくれた上で『感染対策で重要な“一接触介助一手指衛生”ができていません』と的確に指摘してくださいました。密接・密集はリハビリの基本ですから、感染リスクを伴います。患者さんの離床を促し、抑制せずにかかわっている病院や施設にはどこでも起こりうることだと思います」
自分たちの医療は何か――
共有した目標に立ち返る
最初の発熱患者から5日後には患者さんの感染は12人に、スタッフにも感染が判明し、最終的には入院患者100人中75人が陽性、スタッフも27人が感染した。リハビリテーションはクラスター終息まで1か月半にわたり中止。スタッフも多くが濃厚接触者として自宅待機となり、病棟のマンパワーは半減。看護師は夜勤をつなげる看護勤務体制となり、昼間の病棟のケアはリハ職が担うことになった。リハ職にしてみれば、突然リハビリの現場を離れ、配置換えとなったわけだが、それでもとまどいはなかったという。
「私が『今日から業務内容がケアに変わります』と伝えたところ、一致団結して『喜んで』と応えてくれました。リハビリとケア、持ち場は違っても患者さんの必要な機能(筋力や耐久性、日常生活動作)を鍛えたり、弱った意識や意欲を回復させたりするという大きな方向性に変わりはありません。広い療法室でのリハビリはできなくても、隔離された大部屋内でのトイレ介助はリハビリそのものです。病棟でのケアで患者さんを支えることはできると考えてくれたのだと思います」
「患者さんには新型コロナのクラスターが起こったことを説明した上でマスク着用をお願いしたら、患者さんは全員協力してくれました。クラスターはある意味、命の危険のある戦時下ですから、マスクを拒否できるほどの余裕はなかったのです。いや、本当にそんな生易しい状況ではなかったので…」
スタッフの逃げ道をつくるのもリーダーの役割
ところで、肉体的な負担以上にスタッフが苦しめられたのは精神面での負担だった。リハビリのために入院したにもかかわらず、リハビリができない患者さんの不満。感染の責任を攻める家族からの苦情。来る日も来る日もスタッフは怒声を浴びせられた。
「患者さんやご家族にはありのままの事実を説明して、私たちは行政指導を受けながら精一杯やっているとお伝えし、ひたすら頭を下げるしかありませんでした。リハ職や看護師が対応できない場合は現場の医師が対応し、主治医が対応しきれないクレームは私が引き受けました。スタッフを守ることは病院を守ること。院長が最後の砦にならなければいけません。大事なことはスタッフの逃げ道を常につくる気配りなのです」
怒声だけではない。患者さんに対してやってあげたいことを十分に尽くせないということも、真摯に取り組む人を傷つける。時間が経つにつれて、メンタルヘルスを崩すスタッフも現れた。現場が大変なときになかなか自分から休暇を申し出られないスタッフに対して、トップは適切に休養や専門医の受診を勧める必要がある。酒向さんは医師たちと協力してスタッフの面談を行い、メンタルヘルスのアセスメントに取り組んだ。
「何がつらいのかを上長の医師や私に直接話せるようならまだいい。話せなくなっている人こそ問題なのです。私と目を合わせて話ができ、きちんと頭の中の思考が言葉となって出てくるかどうかが、その後の対応を急ぐかどうかのポイントです」
“命令”は届かない
年明けて2021年1月半ば。院内の新規感染者が2週間連続で0人となり、ようやく「ねりまクラスター」は終息し、通常診療を再開した。風評被害も懸念されたが、3月頃からは元のように満床になった。一方、クラスターを乗り越えたスタッフの疲弊はピークに達していた。いわゆる医療者のバーンアウト(燃え尽き)である。クラスター前と同じレベルの質で医療を提供するには、疲弊したスタッフを癒し、再度モチベーションを呼び覚ます必要があった。酒向さんは再び「Back to the basic」を呼びかけた。
「完全復旧のためにどこから着手しようかと考えたとき、頭に浮かぶのはこの病院を何のために開設したか、これまでどういうスタッフ教育をしてきたかということでした。私たちの目指す医療は、患者さんと家族の心と気持ちに寄り添い、リハビリテーション治療によって患者さんが日常生活能力を取り戻すことを一緒に喜び合う医療。スタッフにもその基本に立ち返ってもらいたかった」
こうしなさい、と命令するのは一見簡単そうに見えるが、酒向さんは“命令”はしない。メッセージを直接一人ひとりのスタッフに伝えれば、疲弊しているスタッフが「叱られている」と受け止めてしまうことも恐れた。そこで、酒向さんはさまざまなメディアからの取材の機会を使って、自分の想いを間接的に伝えるという方法をとった。
「“命令”が伝わるのは戦時下だけ。クラスターという戦争が終わり気力の落ちているときに旗を振ってもスタッフには見えません」
「どうすればスタッフがやりがいや夢を持つことができるのか」
それにしても、今回のクラスターは院長である酒向さん自身にとっても厳しい修羅場であり戦時下であったはずだ。“戦後”を含めた4か月半、なぜ折れずに頑張れたのだろうか。
「今、何のために自分が存在するかということに立ち返ると、患者さんと病院、スタッフを守ることに尽きます。クラスターが終息すれば患者さんを守ることはできますが、むしろスタッフのバーンアウトの方が深刻で、院長の自分が壊れている場合ではなかったというのが正直なところですね。トップは孤独なものです。逃げられないし、誰かが助けてくれることもない。この間、私は一日一日の小さな幸せを大事にするようにしました。例えば、眠れなかった方が眠れるようになった、食欲のなかった方が食べられるようになった、笑顔がなかった方が今日は笑ってくれた、便秘の方にお通じがあった――。そんな日々の小さな幸せを大事にしています。また、1~3か月後といった短期的な展望だけでなく、1年、3年、10年、20年、40年先まで計画を持つようにしています。自分の中に短期・長期の両輪の夢と志を持つ。そうでなければメンタルはとても持ちません」
この取材中、何度も「Back to the basic」という言葉が語られた。クラスターという非常事態にあっても、ぶれずにやれることを愚直にやっていく。そのためには組織が戻るべきBasic、トップ自身が戻るべきBasicが何かを日頃から確立しておくことが大切なのだろう。最後にコロナ禍でのリーダーシップとは、と尋ねると、酒向さんはこう答えてくれた。
「トップの役目は、組織をどうコントロールするかではないと思います。コロナ禍にあって、組織の中の一人一人の仲間が、やりがいや夢を見つけるためにどう生きていったらいいのか。それを見つける環境を整えるのがトップの役目、私はそう考えています」
●酒向正春さんの “非常時”に役立つリーダーシップ
できることをこなしていく
理念に忠実であることを忘れない
“ありのまま”を発信する
を築いておく風土は力になる
持てるかを常に考えて行動する
間接的にトップの想いを伝える
ねりま健育会病院の
クラスター発生から終息までの経緯
接触者にあたるスタッフ32人が自宅待機に
陽性患者のうち中等症以上の人が転院
(東京感染症対策センター)の最終確認
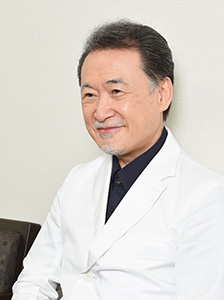
酒向 正春氏
さこう まさはる
大泉学園複合施設
(ねりま健育会病院院長・ライフサポートねりま管理者)
1961年愛媛県宇和島市生まれ。1987年愛媛大学医学部卒。同大学脳神経外科学教室に入局、2003年同講師。2004年初台リハビリテーション病院脳卒中診療科長となり脳リハビリテーション医へ転向。2012年世田谷記念病院副院長・回復期リハビリテーションセンター長、2015年医療法人社団健育会竹川病院院長補佐を経て2017年より現職。ーー 2013年にはNHK「プロフェッショナル〜仕事の流儀〜」第200回でも酒向医師の脳画像解析に基づく「攻めのリハビリ」が注目される。
